毎度の一週遅れのガイアです。見終えました。
入院患者の朝は目覚めたら隣のベッドとの仕切りであるカーテンがまず目に入ってきます。そして白い天井。朝食は8時、昼食は12時、夕食は18時。消灯が21〜22時。このサイクルの病院が一般的かと思うのですが、私の経験上、正直入院するとこのサイクルが毎日続き嫌になります。
手術をうけたり毎日点滴を打たれたりと治療をうけながら余命宣告されると自宅で終わりたいと思うのもすごくわかります。
患者さんやご家族を上からひっぱるのが病院での治療とすると、在宅治療は下から支える土台だよなって思いながら見てました。
患者さんの感謝の涙。ご家族の感謝の涙。それがあるからこそスタッフの頑張り(寄り添い)もあるのでしょうね。
看取る家族をサポートする、本当に力強くありがたい存在だと思います。
今ちょっとプライベートで凹んでおりまして、奈緒さまを拝めてほっこりしました。謝謝。
言葉がもたらす出会い、学び、発見、そして未来を応援することを目的に刊行された雑誌ですが、その雑誌の創刊号インタビューが奈緒さんでした。しかも、第2号に続くとあります。インタビューはECCフォリランのHPにUPされていますが、ECC外語学院でも配布しているそうです。
ということで、今回のテーマは「旅と言葉」です。そのため、奈緒さんの仕事の柱となっている紀行番組について、浮き彫りにしています。直近の「アフリカゾウ」について質問がなされていますが、現地スタッフとりわけゾウの世話をしている人たちとは、いろいろな話をしているように見受けられました。奈緒さんは単なる挨拶に留まらず、ゾウについての質問を投げかけたはずです。訪問したのがケニアと英語圏だったのは幸いでした。
現地の人たちとどう関わればいいのかについて、心構えだけでなく、具体的に言い回しをあげているので、専門学校生のみならず、英語でのコミュニケーションを目指す人に広く役立つことでしょう。
ニューヨークでのエピソードは初めて知るものでした。さすが朝ドラ、外国でも見ている人がいるものです。そして布美枝さんとは違う出で立ちの奈緒さんによくぞ気づいたものだと思います。(どうしても「鶴瓶の家族に乾杯」西伊豆町で、奈緒さんと布美枝さんが結びつかなかった方のことを思い出してしまいます。)そういえばその質問も簡潔なものですが、ちゃんと通じていますね。


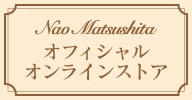






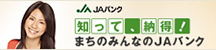

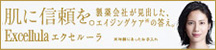



B-blood へ返信する コメントをキャンセル