前半は医療用ガウン、後半はフェイスシールドの話でした。
冒頭で医療従事者が「代用品」に身を包まれている様子が出ていましたが、目を覆いそうになったのが「農作業用プロテクター」をフェイスシールド代わりに使っていることでした。これは堅牢な反面、重くて検査などの業務はしにくいのではないでしょうか。
そんなフェイスシールドについて、奈緒さんが「ある文房具」とヒントを出したところで、クリアファイルを使っていると見当がつきました。角の部分の出っ張りも織り込んで、不具合も解消です。
なまじっかの社長よりもやり手なのでは思われる大阪大教授の営業力に感心しきりでしたが、日ごろの人脈がモノを言った格好です。内視鏡手術をしている様子も出ていましたが、本来はこちらに打ち込むべき方です。医療用具の確保に奔走するのは、医事課あるいは施設課の人の仕事でしょう。
前半のガウンでは、大手航空会社の方々がボランティアに参加している様子が出ていましたが、大ベテランの縫製業者のあとだけにミシンを操作する手つきが何となく危なっかしく見えました。大勢の希望者の中から選抜していること、検品などの後方支援業務が中心ということで、ホッとしました。
奈緒さんの説明にあった日本の医療用具が輸入品に依存していることを、もっと考えなくてはならないでしょう。ガウンでは縫製業者の代表が原材料の確保に四苦八苦していました。食糧自給率のように、医療用具自給率という指標が必要なのではないかとさえ思いました。
次回予告では、軽い衝撃を覚えました。先週の学校、今週の医療用具は、誰もが気づく問題点なので、番組にしやすいでしょう。これに対し、「死生観」は容易には思い浮かばない論点です。テーマ選定の柔軟さを感じさせられます。
一週遅れではありますが、ガイア見ました。今回は我が日本の教育現場からでしたが、オンライン授業そのものの普及具合はこの6月に入ってもまだ進んでいないように感じます。
私の親父が教育現場で従事している者なので、ある程度ではあるのですがその現場の状況について親と電話で話するときに聞くことがあります。親父が勤務している現場がある県では今月からやっと学校を再開するようになりましたが、それでも一部オンラインで授業を進めていかざるを得ない部分があります。しかしながらそれを進めるにあたって新たに通信環境を構築しなければならない他、この教育システムに慣れていないであろう学生さんおよびそのご家庭に理解してもらえるようあらかじめ説明しておく必要があります。さらに今回佐賀県の伊万里小学校の校長先生へのリモートインタビューの中で地元ケーブルテレビと提携してオンライン授業をやっているという話を聞きましたが、親父の所では実際にそのようなオンライン授業をやっているという話自体聞いたことがないので、そのあたりも含めると国内での課題はまだ多いです。今後のことを考えるとオンライン化を一層進めていく必要があるだけに、その整備は急務と言えるでしょう。
また、やはり体育などの実技科目の実習や理科系の科目での実験では今も制限がかかっています。その他、これまで休校が続いていた分その遅れをいかに取り戻すのかも問題になっています。
以上のことを考えると、まだまだ今の教育現場は数多くの難題があると感じます。今かつてない危機にありますが、それを乗り越えるために各々より良い対策をとらないといけないですね。


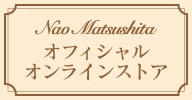






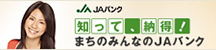

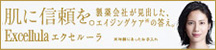



アクエリアス へ返信する コメントをキャンセル