奈緒さん、お集まりの皆さん、こんばんは&お疲れ様です。
今日の「ガイア」は、「コロナで学びを止めるな」ということで、オンライン授業が主でしたね。 日本のオンライン授業の普及率って、こんなに低いんですねぇ~(汗) コロナの今だからではなく、これから新しい感染症が流行した時のために、今からオンライン授業の普及率を向上させる取り組みを推進すべきでしょうね。
日本って、なぜオンライン授業が普及していないのか? それは、師匠が弟子に技を教えて授ける、いわゆる徒弟制度が伝統として残っていることが、その一因なのではないでしょうか?
授業の授は授けるで、授業の業はわざです。 これは、まさに業を授けるということで、師匠が弟子に教える、そのことの名残ではないでしょうか?
対面による教えと学びは、日本の伝統として残しておくべきでしょうが、今回のことで児童・生徒が被った教育を受ける機会のロスは、やはりオンライン授業等のオプションで補填してあげないと、学力低下という、さらに大きな問題を招きかねませんからね。
脱アナログ、もっともっと進めていかないといけないようですね。
それでは奈緒さん、おやすみなさい☆♪
番組ではロンドンの学童保育(に当たるもの)が出ていました。わたしもそちらに関わる機会があり、先月末から子どもたちの学習指導を行っています。学校から出た大量の課題を持て余す子どもが少なからずいて、その対応に追われました。
わたしから見ると「今の教科書は独習できるくらい、親切丁寧に記述してある → 読めばわかる」と思うのですが、やはり「人に教わらない」と理解(わかった!)、いわんや練習問題の解決(できた!)には至らないようです。学校の先生たちが今後の日程のことを考える余り、「課題を出した → 授業では触れない」にならないことを願います。
ご当人は奮闘していても、かつての高等学校講座(現在の高校講座はドラマ仕立てで面白いです)や放送大学みたいな雰囲気が拭い切れない日本のオンライン授業に対し、アメリカや中国は恐ろしく「進んで」います。テレ東の外国取材網が活かされて、番組に広がりが出ていました。
ただ、アメリカでは脱「紙の教科書を使った授業」を果たしたことよりも、学校休業中も給食の提供を続けたことの方を先に取り入れたいと思いました。中国ではソフト化の早いこと!「必要は発明の母」を地で行く話でした。こちらのIT企業では「感染症後の職場」の様子を見ることができましたが、感染症前とそれほど変わりない風景にホッとしました。
奈緒さんは伊万里小学校の校長先生にリモート・インタビューをしていました。学校の授業を再開はしたものの、もろもろの感染症対策あるいは水泳授業ができないなどの制約事項が多くて、恐る恐るやっている感じがよく出ていました。それでも「教育崩壊を止めるのは教育関係者」という言葉に、強い職業意識を感じました。予告を先取りしますが、町工場の方が言う「プライド」に当たるものでしょう。


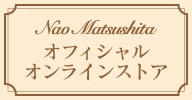






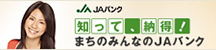

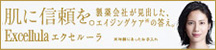



のびもん へ返信する コメントをキャンセル